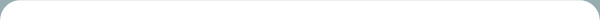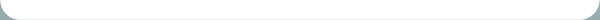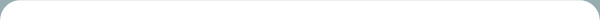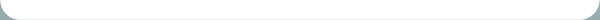時々、コウが分からない。
いやずっと分からない。
オレは、桜坂荘のなかのコウしか知らない―――昔のこと、少しだけ話してくれたけど。
本当は、コウとオレの関係って何なんだろう。
恋人とか家族とか、親友とか、呼び方は色々あると思う。
でも、なにか違うんだ。
何がこんなに不安なんだろう。
コウの周りに、女の子が居て、バレンタインデーだのホワイトデーってイベントが起こっていて。
コウはオレをどういう風に思ってるんだろう。
今年も、大嫌いなホワイトデーがやって来る。
◆◆◆
明日にホワイトデーを控え、今日はコウとクッキーを作る予定だったけど―――。
朝食のあと、マドカとレイを送り出しても、コウは降りてこなかった。
マドカに起こしに言ってもらったら、頭が痛いって機嫌が悪かったらしく、可哀想にマドカは剛速の枕の直撃を食らった。
コンコンッ
「コウ、入るよ?」
返事を待たずに、オレはコウの部屋のドアを開けた。
相変わらず床に色んなものがゴロゴロしている部屋だけど、だいたい何処に何があるかを把握したから、うまく床の部分を踏みながらベッドに近づけた。
頭から布団を被っているコウ。
近くの雑誌の山の上に、薬を載せたお盆を置いた。
「おい、本当に気分悪いんなら病院行って来いよ」
「寝れば直るからいい」
「‥‥お金のこと気にしてるんなら、心配しなくていいからな」
「今、動きたくねーんだ。ほっとけ」
「病人をほっとけるワケないだろ。一応、薬持って来たからさ、飲んどけよ。食後に飲むやつだから、ヨーグルトも持って来た」
ゴソゴソと布団が波打って、ようやくコウが頭を出した。
少し顔色が悪いな。
でも、ニッと笑ってオレを見上げた。
「お前、優しいよな」
その言葉と弱々しげな笑いに、俺は一瞬で鼓動が早くなった。
そんな台詞を、堂々と言われても困る。
だいたい‥‥コウはそんなキャラじゃないだろ!
「ま、まぁ。いいから。ホラ、ヨーグルト食えってば」
「食わせろ」
「食べさせてください、だろ。人にものを頼む時は」
いや、コウらしいんだけどさ。
「食わせろ。起き上がれそうにねーんだよ‥‥」
弱気なんだか、強気なんだか。
オレは、渋々スプーンでヨーグルトを掬って差し出した。
「はい、どーぞ」
なのに、コウはオレの顔ばかり見ている。
「な、なんだよ。毒なんて入ってないよ!?」
「‥‥‥もっと色気がある方法があるだろが」
何を言いたいのか分からなかったのは一瞬で、すぐにコウの思考が読めた。
「ッ‥‥バ、バカ!お前!!熱で脳みそ腐ってるぞ!」
「いーじゃねーか!漫画とかでよくあるだろ!」
「今時ないよ!つか、レイみたいなこと言うなよ!」
「‥‥っ、大声出したら頭が‥‥‥‥」
コウは片手で顔を隠してしまった。
本当に、体調が悪いんだ。
普段ジョギングをしたり、体調に気を使ってるから、こんな風に苦しんでいるコウが心配でたまらなかった。
「コウ、手が邪魔」
コウが「なんだ?」と顔出した。
オレは、ヨーグルトを口に含んだまま、コウの上に被さった。
受け入れるようにわずかに開かれていた唇は、すごく熱かった。
昨日繋いだ手なんかより、ずっとずっと熱い。
「っ、‥‥」
コウの舌は、ヨーグルトを絡め取ろうとする動きじゃない。
「‥‥んっ‥‥!?」
気付いた時は、もう遅い。
布団の隙間から腕が伸びてきて、オレは強い力で抱きしめられた。
いつもよりコウが熱い。
なんだろう、なんか、切なくなってきた。
「コウ、体によく‥‥ないよ」
「いい。このまま、する」
するっていうのは、やはりアレだよな。
そんな体調悪くて、‥‥で、できるのか?
「なぁ、さっきの口移し‥‥もう一回やれよ」
いつもだったら、「バカ」とでも言って突き放したかもしれない。
でも、コウの熱でオレはちょっと惚けてたらしい。
もう一度ヨーグルトを口に含む。
カップをお盆に戻そうとしたのに、コウは待ちきれず俺を引き寄せた。
たぶん、カップはベッドの上に落ちた。
でも、中身はコウのシャツの上と、顔に散ってしまった。
「うわ、冷てー」
コウは顔にかかったヨーグルトを、手で拭おうとした。
オレは、それを制して、舌先でコウの頬を舐めた。
「も、幹?」
思いがけない自分の行動に、オレは慌てて体を離した。
「ご、ごめん。コウが‥‥なんかエロかったから‥‥」
「お前な‥‥」
コウは呆れたように眉を下げて笑った。
そして、もう一度、強く抱きしめられる。
「布団かけてねーと寒いんだよ。しばらく、くっついてろ」
背中にまわっていた腕が、オレのベルトを外しにかかる。
差し込まれた指の熱に、ブルッと震えた。
予想以上に、コウの体温が高い。
「コ、ゥ‥‥手‥‥熱い‥‥」
「そりゃ、熱が出てるからな」
今までとは違うから、オレはすぐに耐え切れなくなる。
すぐに息が上がり、コウに体重を預けた。
声が、我慢できない。
「う、ぁ、コウ‥‥」
名前を呼ぶと、前髪が落ちたコウが、いつもの笑いで口の端を吊り上げる。
いつもなら安心するその笑顔が、今は何故かここ数日の不安感を思い出させた。
オレが知らないコウが多過ぎて、コウが分からなる。
いやずっと分からない。
本当は、コウとオレの関係って何なんだろう。
オレたちは、恋人でも家族でも親友でもない。
なにか違うんだ。
「‥‥コウ」
「ん」
「コウは、オレを何だと思ってる?家族とか、友達とか――恋人、とか」
少しだけ目を閉じて、コウは天井を見た。
「なんだろうな。何って決めて考えたことねーな」
「‥‥そっか」
オレは、切なくて、空しくて、消えたくなった。
どっかにポンッて飛んでけばいい。
「幹は幹でいい、ていうか―――わざわざ家族だとか、恋人だとか、形を決めなくても、ずっと一緒にいてくれれば、それだけでいいんじゃねーの?」
そう言って、コウは一番の笑顔で笑った。
「あー、ごめん。やっぱオレ頭悪いから、うまい事言えねー‥‥」
「そんなこと、ないよ。コウは‥‥オレが一番言って欲しかったこと、言ってくれたから‥‥」
「幹‥‥」
オレは、少し泣いてしまったかもしれない。
ハッキリと、あまりにも確かにコウを好きだ、と思ったから。
もっと、ずっと、コウを―――好きになりたい。
どこもかしこも、コウが熱い。
たぶんオレも。
―――さっきの切なさが募っていく。
たぶんコウも。
「悪ぃけど、自分で挿れてくれよ」
「え、あ、でも‥‥」
「今は、動くの無理だからな。途中で止められないだろ。オレも、幹も‥‥‥」
コウに支えられながら、ちょうど咬み合う場所へ腰を下ろしていく。
クツッと、わずかに拡げられる。
この最初の異物感は、まだ慣れないな。
「―――――っ、コウ‥‥!‥‥あ、っ‥‥う、ぁ―――‥‥‥‥」
異物感は最初の一瞬だけ、あとは体の内側を舐められていくような感覚。
「んん‥‥アッ‥あ、苦し‥‥」
今日は何もかもが、いつもと違っていて、どうしていいか、分からなくなる。
「コウ、コウ‥‥オレ、なんか切ない‥‥くッ―――ひ、ああ‥‥っ」
腹の底、体の奥の方が拡がっていくような、縮まるような、変な感覚がくる。
「幹、お前‥‥‥やばいかも。もう、イきそ‥‥―――――‥‥」
やばいのはオレの方だ、と言いたかった。
でも、今は、息をするので精一杯。
拡がって縮まった一点で、熱い飛沫を受けた。
背中が痛くなるほど仰け反った。
ゾクゾクッと脊髄を快感がせり上がってきた。
太もものが勝手に、わなないて‥‥‥
「うっぁっあっ‥‥‥ッ‥‥あぁ―――――!!」
クタリと、コウの上に落ちる。
コウの心臓の音が大きい。
「幹の心臓の音、すげーな」
オレは、心を読まれたような気がして慌てて顔を上げた。
コウは「どうした?」と不思議そうにオレを見ていた。
まだちょっと切なさが残っていて、キスが欲しくなる。
「コウ、好き。もっと、ずっと、コウを―――好きになりたい」
「こっちの台詞だ、バーカ」
|
|