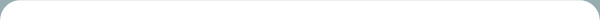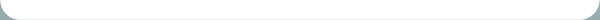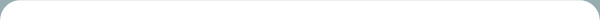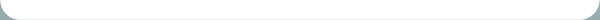好きになりたい
ホワイトデーなんか嫌いだ。
バレンタインデーの「お返し」をする日だなんて、なんか理不尽だと思わないか?
義理チョコなんてヤツに、わざわざ物で「お返し」させるのを強制してると、オレは思う。
だいたい、本命の返事なら一ヶ月も待てない。
「お返し」なんてものに、自分の感情を任せたくない。
◆◆◆
バレンタインデーの桜坂荘は、賑やかしかった。
マドカとレイが、それぞれ紙袋一杯のチョコレートを抱えて帰って来た。
二人とも客商売だし、結構ファンがいるみたいだ。
辰川さんは、数こそ他の2人よりもちょっと少なかったけど、質で勝負って感じかな。
最近テレビなんかでやってる高級店のブランドチョコレートで、これの口溶け感がたまらないんだ。
インタビューで「自分用を買う」と言っていたOLさんが居たけど、その気持ちがわかった。
そして、チョコレートを狙って甘党のスオウさんが顔を出す。
だから、スオウさんが生理的に嫌いなコウが暴れて一騒動が起きた。
その日はなんだかんだで、みんなで騒いで楽しかった。
―――結局、オレとコウは‥‥チョコレートの収穫ゼロだったけど。
オレは、単純に知り合いがいないだけ。
ここに引っ越してきてから、少ししか経っていないから、チョコをくれるような女の知り合いなんかいない。
コウは、全部断ったんだ。
何故かというと、オレたちはちょっと前から「つき合ってる」から。
誰も知らない。
言えない。
でも言いたい。
オレたちは「つき合ってる」って。
悪いことをしてるわけなじゃいのに、マドカとレイにも言えないでいるのは、オレはまだコウとの関係に「怖い」と思っているから。
恋人でも、家族でもない。
このあやふやな、関係に―――。
それから、一ヶ月。
もうすぐ、オレの嫌いなホワイトデーがくる。
―――今日は、俺はコウの買出しに付き合わされた。
スーパーの利用者のほとんどが主婦なのに、催事コーナーにはホワイトデーのお返しが山積みにされている。
会社で義理チョコをもらって来た旦那さんのために、奥さんが買って行くらしい。
郊外型の大きめなスーパーは、広すぎて迷う。
まだ慣れていなくて、レジの前で「あ、アレ忘れた!」と、慌てて引き返すことなんかしょっちゅうだ。
コウは速やかに材料を調達していく。
まるで店内の棚ひとつひとつにいたるまで、どこに何があるかを熟知しているみたいで感心した。
それに、ショッピングカートの上の段はパンなどの軽いもの、下の段はキャベツなど重いもの―――と、きちんと分けてある。
あんなに部屋が荒れ放題なのに、料理に関係することにはちゃんとしてるよなぁ。
生肉コーナーが近くなると、試食で焼かれるソーセージの匂いがしてきた。
焼きたての匂いに、思わずフラフラっと引き寄せられるけど、自分から行ったらコウに「いじきたねー」とか言われるから、今は我慢。
夕飯の材料を品定めしながら、コウとオレはだんだんと試食コーナーに近づいていく。
よし、あと少し!
ふと、試食コーナーに居たバイトの女の子と目が合った。
さぁ来い!
爪楊枝を受取る態勢は整ってますからっ!
出しかけていたオレの手は、その子の次の言葉で緊急停止せざるを得なかった。
「―――コウくん?コウくんじゃない。お疲れ様ぁ」
「あ、どーも。お疲れ様ッス」
コウは驚いて、すぐ満面の笑顔になった。
その反応に、オレは思わず固まってしまった。
コウの、その一番の笑顔を知ってるのはオレだけだって思ってたから。
なんだ‥‥女の子の友達、いるんじゃん。
‥‥‥‥
‥‥‥‥
「うわ~、制服以外のコウくんってはじめて見た。かっこいいね」
「どーも」
コウは、ちょっと照れくさそうな顔をして軽く頭を下げた。
なんだよ、その気持ち悪いっていうか、素直な反応。
それから、オレのことなんか気にも留めずに、コウはその子と話を始めた。
話の内容から、同じバイト先の人だって分かった。
掛け持ちで試食のバイトもしていて、今日はたまたまこのスーパーに派遣されたらしい。
どのくらい、二人は話していただろう。
歳相応に、はしゃいで笑うコウが、オレが知ってるいつものコウじゃなくて―――ちょっと嫌だった。
そうだ、オレって‥‥桜坂荘の外に居る時のコウが、どんななのか知らなかったんだ。
「あ、ねぇ、これ新製品なのよ!ちょっと食べてみて?はい、彼女さんも!」
唐突に仕事を思い出して、営業スマイルですばやくソーセージが刺さった爪楊枝を差し出してきた。
俺に向かって。
‥‥‥‥
‥‥‥‥
ちょっと待て。
「彼女さん」?
「もらっとけよ、カ・ノ・ジョ・さ・ん」
コウは態とらしく、その単語を強調してきた。
ニヤッと口の端を吊り上げている。
オレの中途半端に出されていた手は引っ込めづらく、目の前に積まれていた新製品のソーセージの袋を掴んでカートに放り込んだ。
「ありがと~ございますぅ~」という能天気な声を聞きながら、俺は隣でまだ笑いを噛み殺しているコウの足を思いっきり踏んでやった。
「イッ‥‥テ!」
コウがオレを睨んで来たが、無視、無視!
カートを押して、次へ移動。
コウは「じゃ、また」と手短に挨拶をして、俺を追いかけて来た。
「なんだよ、オレが悪いのか?」
「別に」
極力、感情を抑えて声を出す。
オレが一番むかついてるのは、「彼女」呼ばわりされたことじゃない。
たぶん、それは―――。
「なんだよ、ヤキモチか?」
ムカッ。
軽くキレてしまって、思わず口が滑った。
「‥‥そうだよっ!悪いか!バカ!!」
コウが、片眉を上げて複雑な表情でオレを見た。
無言で。
周りに居た客も、何事かとこちらを見ている。
オレは、下を向いた。
仕方ないだろ。
心の準備が出来てなかったんだ。
オレの知らない話するなよ。
オレが知らないところで、何してるんだよ。
こんな風に誰かが気にするなんて、はじめてだから‥‥怖くなったんだ。
自分が、こんな感情を持ってたなんて。
一番むかつくのは、オレ自身だった。
視界に入っていたコウの黒いスニーカーが近づいてきたから、体が緊張した。
‥‥でも、スニーカーはオレの横を過ぎた。
何かにガッカリして、オレはため息が出そうになった。
ポンポンッと、コウが頭を叩かなかったら、たぶん「はぁ‥‥」って景気が悪くため息を吐いていただろう。
「な、なんだよ。触るな、撫でるな。つーか、なんでニヤニヤしてんだよ!」
見上げたコウは、何故か嬉しそうに笑っていたんだ。
「さっさと帰ろうぜ」
「あ‥‥」
重なった手のひら。
熱い一点。
不意打ちだったから、一瞬体のバランスが崩れてコウに引っ張られた。
「ッ‥‥バカ!放せ」
振りほどこうとしたら、もっと強く握られた。
「手、つなぐぐらいで照れんなよ。ガキだな」
「コウだって、顔赤いじゃん」
「赤くねーよ。お前が赤いんだ」
「ッ‥‥‥‥」
人前で手を繋ぐのが、こんなにドキドキするなんて知らなかった。
いかにも「俺たち付き合ってます」ってアピールしてるワケで。
―――こんな恥ずかしいことは他にない。
「お前、自意識過剰。普通にしてりゃ、誰も気にしたりしないっての」
コウが、いつものちょっと嫌味ったらしい笑顔で、オレを笑った。
皮肉たっぷりのコウの言葉はむかつくけど、いつものコウらしくて、嬉しかった。
「でもさ‥‥‥‥やっぱ目立つだろ?男が‥‥手、繋ぐのは」
オレは小声になっていた。
世間一般から見れば、やっぱりオレたちの関係は特殊。
だからオレたちは、ずっと二人だけの秘密にしている。
好きだってこと。
キスしたことも、その先のことも。
だから、いきなりこんなに人がいる場所で、手を握ってきたコウに戸惑う―――。
「“彼女さん”とだから、違和感ねーよ」
そう言って、コウはとうとう声を出して笑いやがった。
「ばっ‥‥‥や、やっぱ、放せ!オレは女じゃないっ!」
コウは、たぶんそれを言って、からかいたかったんだろう。
シリアスモードになっていたオレって、何だったんだ!?
オレは、あらん限りの力でコウの手を握りつぶし、夕食+クッキーの材料が載ったカートで、コウの足を轢いた。
ちょうど小指にでも当たったんだろう。
コウは声にならない悲鳴を上げて、その場にしゃがみ込んだ。
ザマーミロ、だ。
|
|